社員が辞めるのは給料が安いせい?数字で見抜く人件費と生産性のバランス
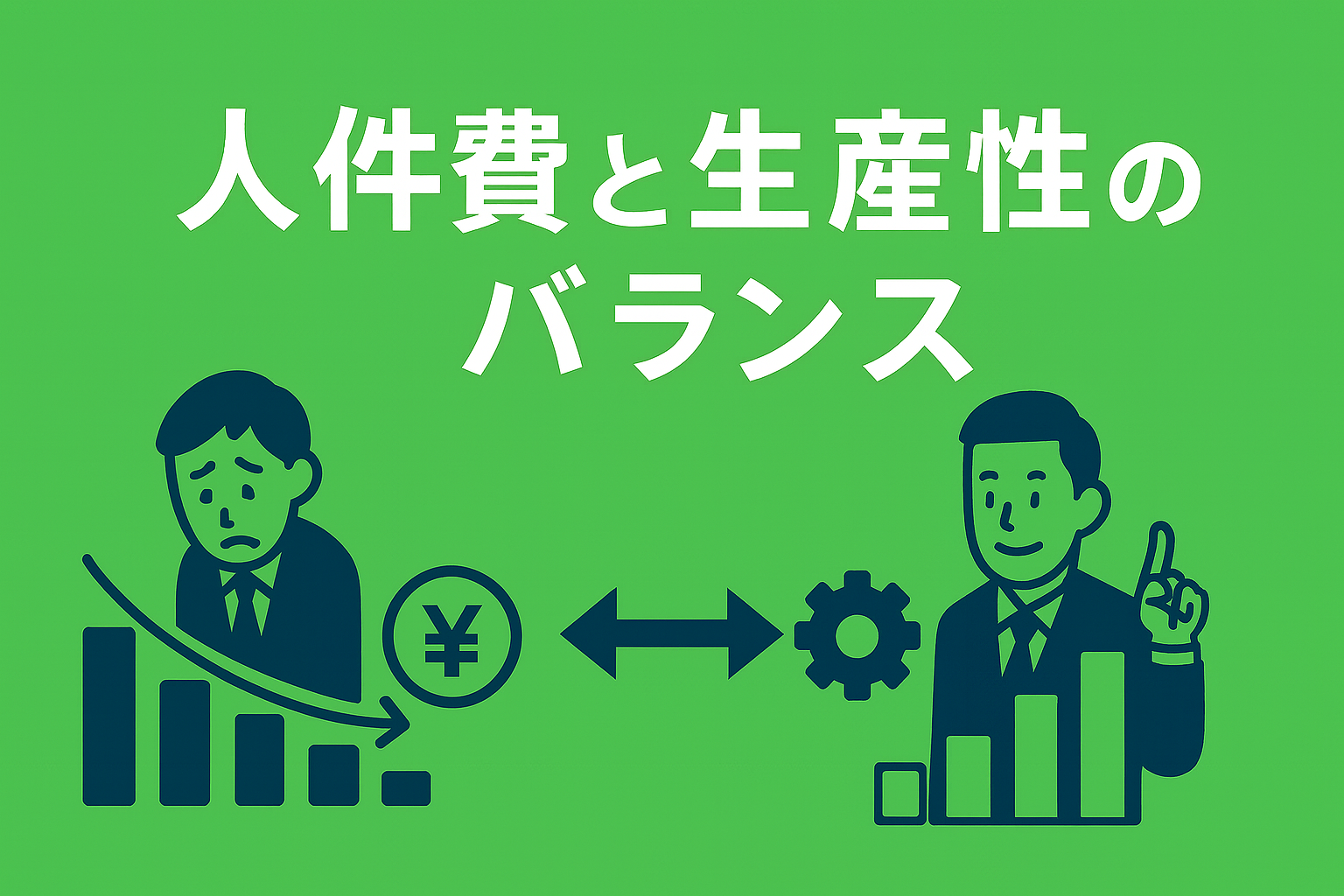
中小企業の経営者にとって、社員の離職は避けて通れない課題です。せっかく採用コストをかけ、時間を費やして育てた社員が辞めてしまうと、現場の業務が停滞するだけでなく、残された社員の士気低下にもつながります。さらに、新たな採用活動を始めなければならず、経営にとって大きなダメージとなります。
そんなとき、多くの経営者が最初に頭に浮かべるのが「うちの給料が安いからではないか?」という疑念です。確かに給与は社員にとって非常に重要な要素であり、納得感のある報酬水準を整えることは欠かせません。しかし、本当にそれだけが離職の原因なのでしょうか。
総務省の「就業構造基本調査」や厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、離職理由として「労働条件(賃金以外も含む)への不満」が上位に挙がる一方で、「人間関係」「将来性のなさ」「仕事内容のミスマッチ」も大きな割合を占めています。つまり、給料が安いから辞めるというケースは確かに存在するものの、それは複数ある要因の一つに過ぎないというのが現実です。
それでも経営者が「給料が安いから辞めたのだろう」と短絡的に考えてしまうのは、理由を数値で把握できていないからです。感覚や噂だけで判断してしまうと、給与を安易に引き上げるなど、経営を圧迫する方向へ舵を切ってしまいかねません。結果として、離職率は下がらず、人件費負担だけが増すという本末転倒の状況に陥る可能性もあります。
ここで必要となるのが「数字で社員の定着と人件費を分析する姿勢」です。人件費の割合や一人あたりの生産性といった数値をきちんと把握することで、給与の妥当性を冷静に判断できます。さらに、退職理由のデータを収集・分析することで、「給与要因」なのか「職場環境要因」なのかを切り分けることも可能になります。
本記事では、以下の流れで「給料が安い」という思い込みを正しく検証し、社員定着につながる人件費と生産性のバランスを数字で読み解く方法を解説していきます。
- 社員の離職理由を「給料が安い」と決めつけないことの重要性
- 人件費と生産性を数値で見える化するための基本指標
- 給与を引き上げるかどうかの経営判断に必要な視点
まずは、離職理由を給与額だけに限定する危うさについて確認していきましょう。
社員の離職理由を「給料が安い」と決めつけていませんか?
社員が辞める原因を「給与の低さ」と断定してしまうと、根本的な解決に至らない可能性があります。
離職理由は複合的で、給与は一要因に過ぎない
離職の原因は一つではなく複合的です。厚生労働省「雇用動向調査」(令和4年版)によると、転職入職者が前職を辞めた理由の上位は「労働条件(労働時間・休日等を含む)」が最も多く、次いで「人間関係」「会社の将来性」「仕事内容の不満」などが挙げられています。「賃金が低いから辞めた」という回答も確かに存在しますが、それは全体の一部に過ぎません。
つまり、給与水準を引き上げても、上司や同僚との関係が悪ければ離職は続きますし、成長の見込みが感じられない会社と判断されれば社員は去っていきます。要するに、給与額の改善が唯一の答えではないのです。
社員アンケートや退職面談で本音を把握する
社員の離職理由を正しく把握するには、アンケートや退職時の面談などの「生の声」を収集することが重要です。特に、退職面談では形式的な質問だけでなく、「どんな場面で不満を感じたか」「もし改善できたら続けたいと思ったか」といった具体的な問いを投げかけることで、給与以外の要因も浮かび上がってきます。
また、在籍社員への定期的なエンゲージメント調査を実施することも有効です。働きやすさや成長機会への満足度を数値化すれば、給与以外の課題を事前に把握し、改善につなげることができます。
離職率と人件費の関係をデータで把握する
もう一つ重要なのが「データでの検証」です。たとえば、自社の離職率と人件費比率(売上に占める割合)を過去数年分で比較してみると、給与が原因で辞めているのか、それ以外の要因が強いのかが見えてきます。
もし人件費比率が業界平均と同等かそれ以上であるにもかかわらず離職率が高いなら、給与以外に根本的な課題が潜んでいると考えられます。逆に、人件費比率が極端に低いのであれば、給与水準が離職の主要因である可能性が高いといえます。
このように、社員の離職理由を正しく見極めるためには、感覚ではなく「数字」と「声」を組み合わせて分析することが不可欠です。次章では、そのために有効な「人件費と生産性のバランスを測る指標」について解説していきます。
人件費と生産性のバランスを「数値」で見える化する
人件費と生産性のバランスを把握することは、経営の健全性を維持するうえで欠かせません。感覚や経験だけで「給与は高いはず」「人件費が重いから」と判断するのではなく、数値的指標を用いることで、経営判断の根拠が明確になります。特に中小企業では、数字に基づいた意思決定を行うことが、離職対策や投資判断の精度を大きく高めます。
「労働分配率」で人件費の重さをチェックする
最も基本的な指標は労働分配率です。これは「人件費 ÷ 付加価値額」で算出され、社員が生み出した付加価値のうち、どれだけを人件費に充てているかを示します。
たとえば労働分配率が70%を超えている場合、利益が圧迫されやすく、会社としては将来の投資余力が乏しくなります。一方で50%を大きく下回ると、社員への報酬が少なく、モチベーション低下や離職率の上昇につながるリスクが高まります。
このように労働分配率は、給与の水準を「重すぎるのか、適切なのか」を客観的に見極める目安となります。
「人件費率」を業種別に比較してみる
次に有効なのが人件費率です。これは「人件費 ÷ 売上高」で求められ、売上の中で人件費がどれだけの割合を占めているかを示します。
人件費率は業種によって大きく異なります。たとえば、サービス業では人件費率が40%を超えるケースが珍しくありません。一方、小売業では10〜15%程度が一般的です。このように業種ごとに標準的な水準がまったく違うため、自社単独で「人件費が高い」と判断するのは危険です。
もし自社の人件費率が業界平均より高く、利益率が低ければ、人件費が過重になっている可能性があります。逆に業界平均より低ければ、社員にとって給与が見劣りし、採用や定着で不利になる恐れがあります。
「一人あたり付加価値額」で生産性を測定する
最後に注目すべきは一人あたり付加価値額です。これは「付加価値額 ÷ 従業員数」で算出され、従業員一人がどの程度の価値を生み出しているかを示します。
この数値を給与と比較すると、「社員に支払っている給与は、その人が生み出す成果に見合っているのか」を判断できます。たとえば、一人あたり付加価値額が500万円で、平均給与が400万円なら、付加価値に対して妥当な水準といえます。しかし、付加価値が低いのに給与だけを上げてしまうと、経営の持続可能性が損なわれます。
一人あたり付加価値額は、社員一人ひとりの貢献度を可視化するうえでも有効であり、評価制度や給与体系の改善に直結します。
このように、労働分配率・人件費率・一人あたり付加価値額といった指標を活用することで、人件費と生産性のバランスを客観的に評価できます。重要なのは「感覚ではなく数字で見る」姿勢です。次の章では、これらの数値を踏まえたうえで「給与を上げるべきかどうか」の判断軸について整理していきます。
「給与を上げるべきか?」の判断に必要な3つの視点
給与を上げるかどうかは、単純に「社員が不満を持っているから」では決められません。企業の財務状況や市場環境、人材の貢献度を踏まえて判断する必要があります。ここでは、経営判断に欠かせない3つの視点を整理します。
業績に見合った給与かどうかを検証する
給与を引き上げるかどうかは、まず自社の業績とのバランスを見極める必要があります。利益やキャッシュフローが安定していないのに給与を大幅に上げてしまうと、資金繰りが逼迫し、経営の持続可能性が危うくなります。
反対に、利益が増えているのに給与が据え置かれている場合は、社員が「会社は利益を独占している」と感じ、モチベーションを失う可能性があります。つまり、業績に応じて給与を適正に配分する仕組みが重要です。
市場相場と自社給与を比較して競争力を確認する
次に考えるべきは、同業他社との比較です。採用市場においては、給与水準が大きな判断材料になります。たとえば、同業種の平均給与が年収400万円なのに自社が350万円であれば、採用・定着で不利になるのは明らかです。
厚生労働省や業界団体が発表する統計データを参考にしながら、自社の給与が市場相場に対して適正かを定期的にチェックしましょう。相場から大きく外れている場合は、修正が必要です。逆に、相場と同等かやや高い水準であれば、「給与以外の魅力」を強化することが有効です。
生産性の高い人材に報いる評価制度の整備
最後に重要なのが、評価制度のあり方です。全員一律の給与引き上げは、業績への貢献度が高い人材にとって不公平感を生み、逆に離職を招く可能性があります。
成果やスキルに応じた報酬制度を整えることで、生産性の高い社員を適切に評価できます。たとえば、一人あたり付加価値額を評価基準に取り入れる、またはプロジェクトごとの成果を可視化して給与に反映する仕組みなどが考えられます。こうした制度は、給与水準そのものよりも社員の納得感を高め、定着率向上につながります。
給料が安いことが原因かは「数字」で見抜くべき
社員が辞める原因を「給料が安いから」と短絡的に決めつけることは危険です。給与は重要な要素であることは間違いありませんが、離職理由は複合的であり、給与以外の職場環境や成長機会の不足が大きな影響を与えるケースも少なくありません。
だからこそ、感覚ではなく数字で判断することが求められます。労働分配率、人件費率、一人あたり付加価値額といった指標を用いて人件費と生産性のバランスを把握すれば、自社の給与体系が妥当かどうかを客観的に確認できます。さらに、社員アンケートや退職面談を通じて定性的な情報を補うことで、離職の真因を見極めることが可能になります。
そして給与を引き上げる判断を下す際には、①業績とのバランス、②市場相場との比較、③生産性の高い人材への適切な評価という3つの視点を持つことが不可欠です。この視点を持たずに給与を一律に上げてしまえば、経営を圧迫するだけでなく、社員の不満を解消できないまま離職が続く恐れがあります。
重要なのは、数字を根拠にした冷静な経営判断です。そして、もし社内での分析や制度設計が難しいと感じるなら、専門家の力を借りるのも有効な手段です。バックオフィス代行やCOO代行サービスは、人件費管理や生産性分析をサポートし、経営者が正しい判断を下せる環境を整えます。
「給料が安いから社員が辞める」と思い込むのではなく、数字で真実を見抜き、社員と会社の双方にとって納得できるバランスを追求すること。それが、持続的な組織づくりへの第一歩となります。









