節税のつもりが資金繰り悪化?陥りやすい決算対策の落とし穴
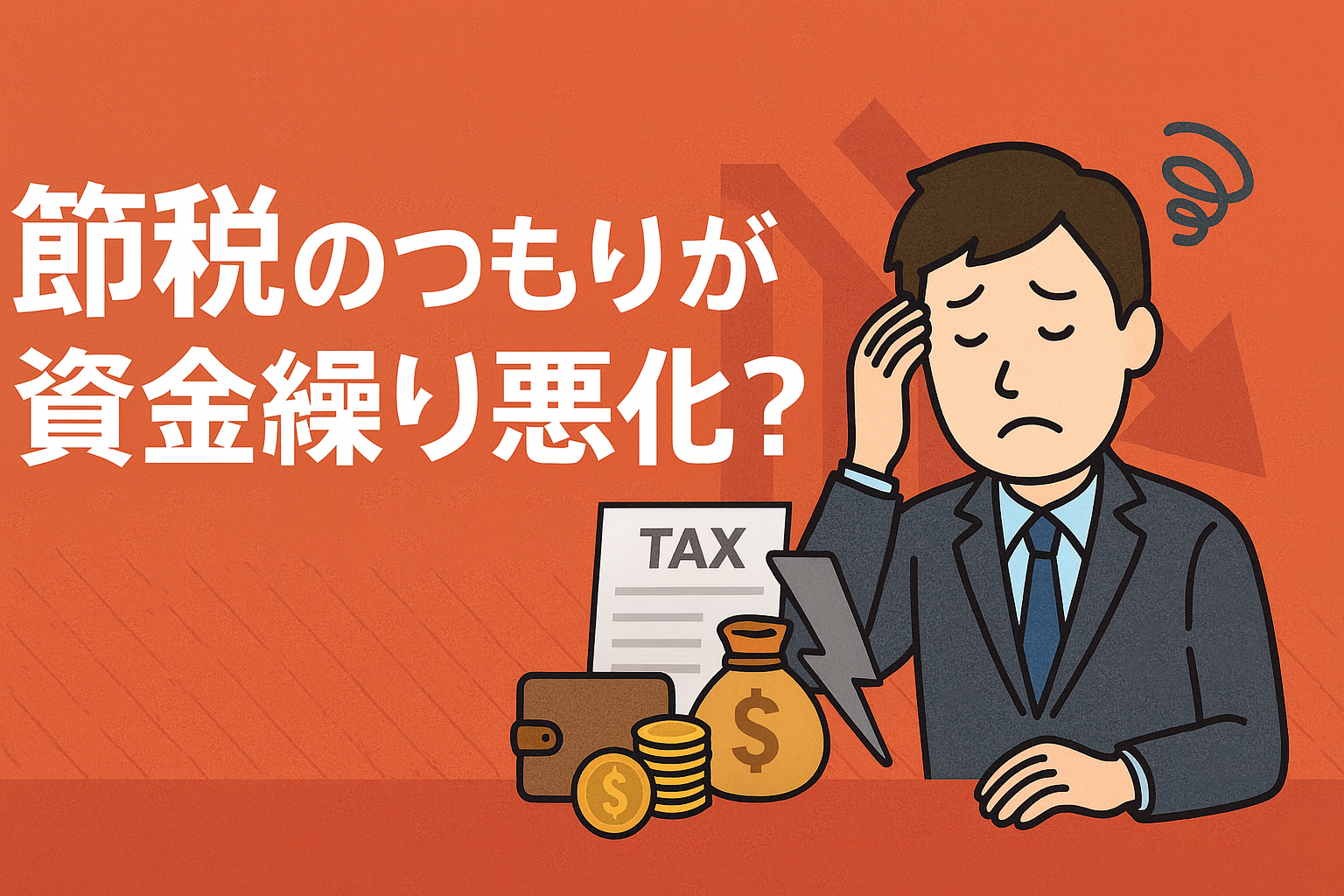
「節税=会社にお金を残す手段」──これは多くの経営者が抱く考えかたです。
確かに、税金を払わないように節税を頑張ったほうが手元に資金を残せるように感じます。しかし現実には、「節税に取り組んだのに、翌月の資金繰りが苦しい」という矛盾した状況に陥る中小企業は少なくありません。
その背景には、決算直前に実行される「節税対策」があります。顧問税理士から「今のままでは法人税がいくらかかります」「この設備を買えば節税できます」と助言を受け、慌てて実行した経験をお持ちの社長も多いのではないでしょうか。確かに納税額は減りますが、その結果として資金繰りが悪化し、かえって会社経営を不安定にしてしまうことがあるのです。
ここで大切なのは、税務の数字と資金繰りの数字は一致しないという事実です。損益計算書の利益を減らせば税額は減りますが、それと「現金が増える」ことは必ずしも連動しません。むしろ、節税によって資金の流れを止めたり遅らせたりすることで、資金繰りにマイナスの影響を及ぼすケースが多いのです。
本記事では、財務の専門家が実務で見てきた中小企業の事例を踏まえつつ、「節税が資金繰りを悪化させる落とし穴」を解説していきます。
節税が資金繰りを悪化させるメカニズムとは?財務の専門家が見る3つの盲点
納品や工事完了の売上計上のタイミング調整による“合法的節税”でも資金繰りを圧迫する
商品の納品や工事の完了を翌期に遅らせて売上計上を先送りする節税策は、資金繰りを悪化させる可能性が高いのです。
この方法は決して違法ではありません。契約上の取り決めや工事進行具合の実態に基づいて、納品日や完成検査の時点が翌期にずれることは珍しくなく、その場合は売上計上も翌期に行うことが会計ルール上でも適切です。そのため「合法的な節税」として実務の現場でもしばしば活用されています。
しかし、ここには大きな盲点があります。売上計上が翌期になるということは、その売掛金の回収も当初の予定月よりも遅れてしまうという点です。つまり法人税は軽減されても、運転資金に必要なキャッシュインが遅くなってしまい、翌期首以降の資金繰りが苦しくなるのです。
例えば、決算月が12月末の会社の場合、12月末に納品予定だった1,000万円の商品を、顧客の理解を得て1月初旬に納品を遅らせたケースを考えてみましょう。帳簿上での売上計上も 翌期に回るため、利益も翌期になり、結果的に単年度の法人税は軽減されます。しかし実際には、12月に予定していた売掛金の発生と翌月の入金が後ろ倒しになるため、年始に予定していた資金繰りが狂ってしまいます。その結果、年末賞与の支給や仕入代金の先行的な支払いに資金が足りず、短期借入に頼る羽目になってしまいます。
節税効果があったとしても、借入に伴う金利や信用コストを考えれば「節税どころか損をした」というケースも少なくありません。結論として、売上計上のタイミングを操作して節税を図ることは、資金繰りに余裕がない会社にとっては危険な選択だと言えるでしょう。では、費用計上を増やすことで節税を狙った場合にはどうなるのでしょうか。
「費用計上=節税」への過信がもたらす資金減少の罠
次に多いのが、「費用を増やせば節税になる」という考え方です。確かに損益計算書の上では、費用が増えれば利益が減り、結果的に納税額も減少します。
しかし問題は、費用を計上するためには多くの場合、現金の支出を伴うという点です。帳簿上は節税に成功したように見えても、その実態は「キャッシュが減っただけ」ということも珍しくありません。
たとえば、決算直前に役員退職金や決算賞与を支払うケースがあります。退職金や賞与は損金算入できるため、多額の節税効果が見込めます。しかし実際には現金での支出が一度に発生し、会社の資金を圧迫します。支払った金額が大きければ、その後の運転資金に影響を与え、急な支払いに対応できません。
また、法人保険や備品購入なども同様です。確かに損金算入できれば税額は減りますが、現金はその時に流出します。しかもそれらの支出が必ずしも事業に直結するものでなければ、「節税のために無駄な支出をした」だけになってしまうのです。
「費用を使えば節税になる」という短絡的な考えは危険です。費用計上による節税策は、その効果と同時にキャッシュフローへの影響を必ず検証する必要があります。では、こうした「節税優先」の思考がどのように財務戦略を歪めるのかを見てみましょう。
税務上のメリットが先行しすぎると財務戦略が崩壊する
節税策を追い求めすぎると、会社全体の財務戦略が歪んでしまうことがあります。
本来、財務戦略は「資金をどう循環させ、事業成長に投資するか」を設計するものです。しかし、節税だけを優先してしまうと、短期的な税メリットにばかり目が行き、中長期の資金繰りや投資計画が後回しになってしまいます。
例えば、決算直前に「仕入を増やせば利益を圧縮できる」と考え、在庫を積み増すケースがあります。しかし実際には、在庫は費用ではなく資産として計上されるため、販売が行われない限り原価には算入されません。したがって、当期の利益を減らす効果は得られないのです。
さらに問題なのは、資金が「在庫」として固定化されてしまう点です。その商品が売れなければ現金化できず、資金循環が停滞することで運転資金に余裕がなくなる可能性があります。
在庫の積み増しは「節税策」にはならないどころか、資金効率を下げるリスクの方が大きいと認識する必要があります。
つまり、節税は財務戦略の一部であっても、主役ではないのです。短期的な税負担軽減に気を取られて財務全体のバランスを崩せば、会社の資金基盤そのものを弱体化させてしまいます。
“税金はコスト”という誤解がもたらす資金運用の非効率
多くの経営者が口にする言葉に「できるだけ税金を払いたくない」があります。気持ちは理解できますが、税金を「コスト」と誤解している限り、正しい資金運用はできません。税金を減らすことだけに執着すると、せっかく得られるはずの資金余力を自ら放棄してしまうことになります。ここではその代表的な3つの誤解を整理していきます。
税金を「払わない戦略」ではなく「払っても残る戦略」へ転換を
税金を払ってでも会社に資金が残る経営こそが本質的に健全な会社の姿です。
なぜなら、法人税を支払うということは利益が出ている証拠だからです。むしろ黒字の会社は、税金を納めつつも十分な内部留保を積み重ねることで、自己資本比率を高め、金融機関等のステークホルダーからの信用も得られるようになります。
例えば、ある会社が1,000万円の利益を計上し、300万円の法人税を支払ったとします。残りの700万円は内部留保として会社に残ります。一方、節税を優先して利益をゼロに近づけるような決算対策をした場合、確かに税金は減りますが、会社に残るキャッシュも減少し、自己資本も積み立てることができません。翌期の設備投資や急な資金需要に対応できず、結局は借入に頼らざるを得ないケースも少なくありません。借入という他人資本が増えると、自己資本比率は更に下がるという悪循環に陥ってしまいます。
「税金を払う=損」ではなく、「税金を払う=資金が残っている証」という考え方への転換が必要です。
節税を「年一イベント」にしない。通年での資金設計の重要性
次に重要なのは、節税を決算前だけのイベントにしないことです。
多くの中小企業は「決算間際になってから利益が出そうだから節税対策を考える」という動きをします。しかしこれでは、どうしても短期的で場当たり的な判断に陥りやすく、キャッシュフローへの影響を読み切れません。
本来あるべき姿は、通年を通して資金計画や利益計画を立て、その中で節税策を検討することです。月次決算や四半期ごとのシミュレーションを行えば、利益の着地点をある程度予測でき、決算直前に慌てて設備投資や保険契約をする必要もなくなります。
例えば、12月決算の会社の場合でいうと、9月の時点で利益予測を確認し、法人保険や研究開発投資の実行を検討すれば、年末に無理な支出を急いで行わなくても済みます。資金繰りを圧迫することなく、計画的に節税を実現できるのです。
節税は年一回の決算対策ではなく、年間を通じた資金設計の中に組み込むべきものであると言えます。
「税引後利益」と「キャッシュ残高」は一致しない事実を理解する
最後に押さえておくべき大前提は、損益計算書の数字と実際のキャッシュ残高は一致しないという事実です。
例えば、減価償却費は会計上の費用ですが、実際には現金支出を伴いません。一方、売掛金や棚卸資産は損益計算書上は売上や原価として反映されても、現金化されるタイミングは異なります。つまり「黒字なのに現金がない」「赤字なのに現金が残っている」という現象が普通に起こり得るのです。
典型的なケースとして、2,000万円の黒字を計上した会社が、売掛金の回収が遅れて現金残高は100万円しかない、という場合も十分に考えられます。損益計算書上は健全でも、実際の資金繰りは危機的状況です。逆に、減価償却費の影響で赤字に見えても、現金は潤沢に残っているというケースもあります。
したがって、経営者は「税引後利益」だけで会社の健全性を判断してはいけません。重要なのはキャッシュフロー計算書を用いて、資金の動きそのものを把握することです。
税金を単なるコストと考えるのは誤りです。税金は会社に利益が出ている証であり、払っても資金が残る経営を目指すことが本質的なゴールです。また、節税を決算前の一時的な対策にせず、通年の資金設計の中で取り入れることで、資金繰りへの悪影響を避けることができます。そして何より、帳簿上の利益とキャッシュ残高は異なるという事実を常に意識しなければなりません。
これらを踏まえると、節税と資金繰りを対立させるのではなく、両者を統合的に設計する「財務戦略」の視点が欠かせないことが見えてきます。次の章では、そのための具体的なアプローチについて解説していきます。
節税と資金繰りを両立させる「統合型財務設計」のすすめ
ここまで見てきたように、節税策を単独で追求すると、資金繰りを悪化させる危険性が高いことがわかります。
では、どうすれば「節税」と「資金繰り」を両立させ、会社にお金を残すことができるのでしょうか。その答えが、統合型財務設計です。
統合型財務設計とは、損益計算書の利益だけに注目するのではなく、キャッシュフロー計算書や資金繰り表を含めた財務全体の視点から、節税策の妥当性を判断する考え方だと定義しています。以下では、その具体的なポイントを3つに整理して解説します。
計上の仕方一つで税負担と資金計画は変わる
同じ支出でも、会計上どの勘定科目で処理するかによって、税金の負担時期や資金計画の立てやすさが変わります。
例えば、ソフトウェアを導入したとき、少額であれば「消耗品費」として当期に一括費用として計上できます。一方で「無形固定資産」として資産に計上し、数年かけて減価償却として費用化する方法もあります。
処理を一括費用とすれば、その期の利益が減り法人税も軽くなります。しかし翌期以降には節税効果が残らず、毎年の利益予測や資金繰りの見通しは不安定になりがちです。逆に資産計上をすれば、今期の税負担は減りませんが、毎期計画的に費用化されるため、中長期の利益計画は立てやすくなります。
大事なのは「どちらが税金を少なくできるか」ではなく、「どちらの処理が自社の資金繰りや経営計画に合っているか」という視点です。節税だけで判断するのではなく、企業経営全体に与える影響を考えて処理を選ぶことが、統合型財務設計の第一歩になります。
支払と回収のタイミングを設計し、資金不足を未然に防ぐ
節税に目を奪われると見落とされやすいのが、支払と回収のタイミング設計です。利益や税額だけを気にしていても、実際の資金の出入りが読めていなければ、資金繰りはすぐに行き詰まります。
例えば、売上が立っても入金が2か月後である一方、仕入代金は翌月に支払う契約だったとします。この場合、会計上は黒字でも、キャッシュは不足し、運転資金がショートしかねません。
加えて、決算期前後には賞与や納税といった大口の支出が集中することが多く、この時期の資金繰りには特に注意が必要です。資金繰り表で支出の山を見える化し、事前に準備をしておくことが欠かせません。
さらに一歩踏み込むなら、営業活動の段階で資金繰りを意識することが重要です。大口案件や長期プロジェクトの場合、販売先と交渉して前受金や着手金をもらう仕組みを取り入れれば、決算前後の資金負担を大きく和らげることができます。特に建設業やシステム開発業などでは、契約時点で一部を回収する慣行もあり、これを積極的に取り入れることで資金計画は格段に安定します。
節税策を実行する前に、支払と回収のサイトを調整し、営業活動においても資金回収の前倒しを意識することが、資金繰り安定のカギです。
キャッシュフロー計算書から始める意思決定の精度向上
節税と資金繰りのバランスを取る最も効果的な方法は、意思決定の起点を損益計算書ではなくキャッシュフロー計算書に置くことです。
多くの経営者は「利益が出ているから大丈夫」と考えがちですが、黒字倒産という言葉が示すように、利益と現金残高は必ずしも一致しません。そこで重要になるのが、営業CF・投資CF・財務CFの3区分で資金の流れを整理することです。
例えば、決算賞与の支給や設備導入を検討する際に、キャッシュフロー計算書で「支出のタイミング」と「翌月以降の入金予定」を照らし合わせるだけでも、資金ショートを回避できる確率は格段に上がります。
また、毎月の資金繰り表を作成し、3か月先までのキャッシュ残高を予測する習慣を持つことも効果的です。これにより、「今やるべき節税策」と「後回しにすべき支出」を明確に切り分けられるようになります。
キャッシュフロー計算書を意思決定の基盤に置くことが、統合型財務設計の中核であり、節税と資金繰りを両立させる唯一の方法と言えるでしょう。
節税よりも“資金を残す経営”を選ぶ覚悟を
節税はそれ自体が目的ではなく、会社にお金を残すための手段の一つにすぎません。
しかし、節税を優先するあまり資金繰りを悪化させてしまう中小企業は意外に多くあります。その原因は、「税額の軽減」と「資金の確保」を混同していることにあります。
経営者が本当に見るべきは「税額の大小」ではなく「キャッシュ残高の推移」です。そのためには、損益計算書に表れる利益だけでなく、キャッシュフロー計算書や資金繰り表を用いて多面的に財務を捉え、統合的な設計を行うことが不可欠です。
財務分析を税理士任せにするのではなく、経営者自身が財務の全体像を理解し、主体的に判断する姿勢が求められます。そして、その判断を支える道具としてキャッシュフロー計算書や資金繰りシミュレーションを活用し、必要に応じて外部の財務専門家を取り入れる柔軟さを持つことが大切です。
「節税=会社を守る」ではなく、「資金を残す=会社を守る」──。
この発想の転換こそが、資金繰り悪化の落とし穴を回避し、会社を持続的に成長させるための最も重要な鍵なのです。









