経費のムダを見抜く!固定費・変動費の徹底チェック法
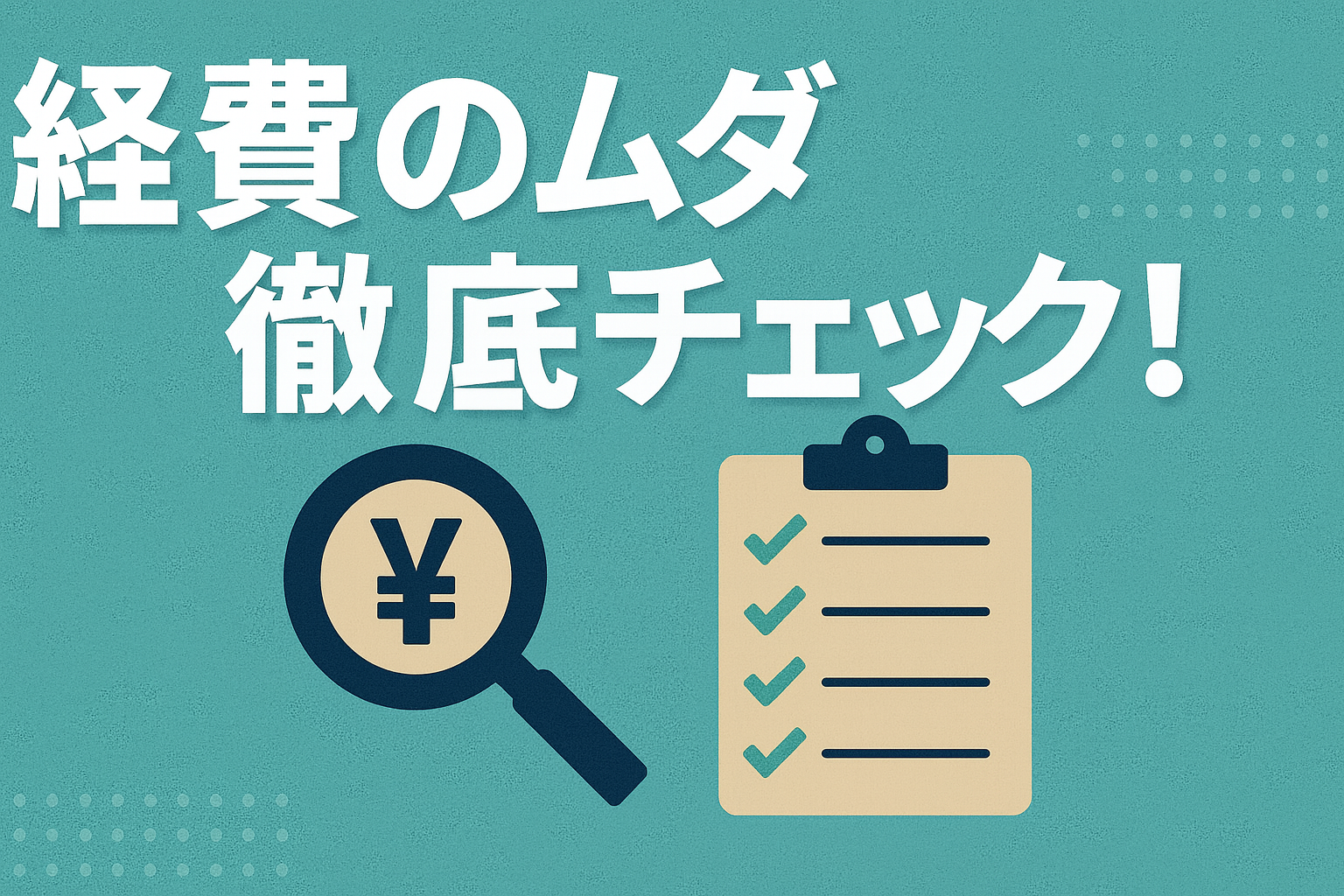
中小企業の経営において、「売上を増やすこと」と同じくらい重要なのが「経費のムダを減らすこと」です。利益を確保するうえで、ムダなコストを削減する効果は非常に大きく、即効性もあります。しかし実際には「どの支出が必要で、どの支出が削れるのか」がはっきりせず、感覚的な判断に頼ってしまっているケースが少なくありません。
その問題を解決するカギとなるのが、「固定費」と「変動費」という視点です。固定費と変動費を明確に区分することで、自社のコスト構造が可視化され、改善の優先順位が分かるようになります。固定費の削減は経営の安定性に直結し、変動費の削減は利益率の改善に直結するため、この両者を正しく理解し管理することが経営改善の第一歩となります。
本記事では、まず固定費と変動費の基本的な違いと経営への影響を整理し、そのうえで「ムダを見抜く」ためのチェック方法へと説明を続けていきます。
固定費・変動費の違いと経営への影響
固定費と変動費の特性を理解することは、会社の経費構造を把握し、戦略的に改善していくうえで不可欠です。両者の性質を知ることで、どこにムダが潜んでいるのかが見えてきます。
固定費は「長期的な負担」であると意識する
固定費は、売上や業務量の変動に関係なく、毎月必ず発生する支出です。代表例はオフィス家賃・正社員の基本給等の人件費・リース料・管理費的費用などです。これらは企業活動の土台を支える一方で、売上が減少しても支出額が減らないため、経営を圧迫する要因となります。
たとえば、広すぎるオフィスを借りていたり、利用頻度が低い設備を維持していたりすると、それらは売上と無関係に毎月会社の資金を消費します。こうした固定費は「長期的に体力を削る存在」であると認識し、定期的に見直すことが重要です。
変動費は「売上に比例する支出」である
変動費は、固定費とは逆で、売上や業務量に応じて増減する支出です。代表例は材料費・仕入原価・外注費・配送費・販売手数料などです。売上に比例するため、需要の変化に合わせて自然に増減します。
変動費は「仕方のないコスト」と思われがちですが、実は効率化によって改善できる余地が大きい項目です。たとえば、仕入れ先との価格交渉、原材料の無駄削減、外注の内製化、物流ルートの見直しなどで利益率を高められます。売上を伸ばすことが難しい場合において、変動費の改善は会社の競争力を支える大きな武器となります。
固定費と変動費の「境界」にこそムダが潜む
実務では、固定費と変動費の分類があいまいな支出が少なくありません。たとえば、毎月定額で発生している外注費や、利用頻度の低いクラウドサービスのサブスクリプション費用などです。これらは本来変動費であるべきものが「実質的固定費」として会社を圧迫していることがあります。
こうした“隠れ固定費”は、社内で見過ごされやすい一方で、大きなムダの温床になりやすい領域です。分類を明確にするだけで、改善の優先順位がはっきりし、削減効果も大きくなります。
固定費と変動費の性質を正しく理解し、さらに境界に潜むムダを意識することで、自社のコスト構造を客観的に把握できるようになります。この基礎を踏まえた後に、「数字でムダを見抜く具体的なチェックポイント」の説明に進みます。
経費のムダを発見するためのチェックポイント
経費のムダを削減するためには、勘や経験ではなく「数字」を根拠に判断することが欠かせません。数字で可視化すれば、思い込みや慣習に隠れていた支出が浮かび上がり、改善の優先順位が明確になります。ここでは、経営者やバックオフィスの責任者が実践しやすい3つの分析視点を紹介します。
月次損益計算書を「縦」ではなく「横」で見る
多くの経営者は毎月の損益計算書を確認しますが、単月だけを売上から始まり、費用があり、利益で終わるという「縦」で見ていては異常が見えにくいものです。数か月から1年分の損益計算書を「横」に比較することで、支出の推移が明確になります。たとえば、売上が下がっているのに外注費が一定額のまま発生していれば、それは実質的な固定費であり、ムダの可能性が高いと判断できます。Excelや会計ソフトで推移表を作り、月別のトレンドをチェックする仕組みを持つことが重要です。売上高や各経費項目を横に並べるだけで、気づかなかったコストが浮き彫りになることは少なくありません。
勘定科目ごとの「比率」を分析する
経費を金額ベースで把握するだけでは十分ではありません。売上に対する比率を計算することで、経費の重みを相対的に評価できます。例えば、仕入原価率が前年より数ポイント高い場合や、広告宣伝費率が業界平均を大きく上回っている場合は、改善の余地があると判断できます。比率分析は、単なる支出額の大小ではなく「効率性」を示してくれるのが強みです。さらに、比率の推移を社内で共有すれば、部門間で共通の指標として活用でき、コスト意識の醸成にもつながります。
部門別・プロジェクト別に経費を紐づける
全社単位で経費を集計しているだけでは、具体的なムダの所在は特定できません。部門別やプロジェクト別に経費を仕分けることで、非効率がどこに潜んでいるかが明確になります。たとえば、ある部署だけ残業代が突出している、特定のプロジェクトにだけ広告宣伝費が集中している、というような状況です。こうした分析を行うと、単なる「経費削減」ではなく「業務改善」へと議論を発展させることもできます。さらに、部門ごとに経費を可視化することで、現場の管理職やスタッフの当事者意識も高まり、経費削減が組織文化として根付いていきます。
これらのチェックポイントを持つことで、経営者は感覚に頼らずに客観的な判断を下せるようになります。次は、発見したムダを一時的な削減に終わらせず、継続的に改善できる仕組みにする方法を考えていきましょう。
固定費・変動費の見直しを仕組み化する方法
経費の削減は、一度のチェックで終わらせると効果が持続しません。固定費・変動費の見直しを「仕組み」として社内に根づかせることで、継続的な改善が可能になります。ここでは、組織的に取り組むための3つの方法を解説します。
定期的な経費レビュー会議を導入する
経費削減を仕組み化する第一歩は、定期的なレビューの場を設けることです。月次または四半期ごとに経費をチェックすることに重点をおいた会議を設定すれば、経費の動きをタイムリーに把握できます。
このとき重要なのは、単に「削減しよう」と迫るのではなく、数字をベースに客観的に議論することです。例えば「外注費が3か月連続で一定額発生しているが、売上との連動が見られない」といった事実を示すと、担当者も納得感を持って対応できます。定期的なレビューは、現場の小さな改善を積み重ねる仕組みとして効果的です。
経費の「KPI化」で意識改革を促す
次のステップは、経費を数値目標として管理することです。売上や利益のKPIと同様に、「経費率」「部署ごとの外注費比率」「広告宣伝費のROI」などをKPI化すれば、部門ごとに責任を持ってコストを管理できるようになります。
経費のKPI化は、単なるコスト削減のためだけではありません。数値で目標を設定することで、各部署が自ら工夫し、経費の使い方を最適化しようとする意識が生まれます。例えば、営業部が広告宣伝費の投資効果を測定しながら予算配分を工夫する、総務部が残業時間を削減して人件費率を下げる、といった取り組みです。経費のKPI化は「数字を使って考える文化」を醸成し、会社全体の財務体質を強くしていきます。
外部パートナーの視点を取り入れる
社内だけで経費を見直そうとすると、慣習や思い込みに縛られてしまうことがあります。そこで有効なのが、外部パートナーによる第三者の視点です。例えば、会計事務所やバックオフィス代行サービスなどに定期的なレビューを依頼すれば、社内では気づきにくい非効率や改善余地を明確に指摘してもらえます。
特に中小企業の場合、経営者や管理部門のリソースには限界があります。外部の専門家を活用すれば、経費の可視化や改善提案を効率的に進められるでしょう。必要に応じて部分的にアウトソーシングすることも、仕組み化の選択肢のひとつです。
数字を味方にすれば、ムダは必ず見える
経費削減は「やみくもに削る」ことではなく、「数字で可視化し、合理的に判断する」ことが重要です。固定費と変動費を正しく区別し、それぞれの性質に応じて管理すれば、社内のムダは必ず浮き彫りになります。
固定費は長期的に企業体力を削るリスクがあるため、定期的に見直しが必要です。一方で変動費は、効率化や交渉によって利益率を改善できる余地が多く残されています。さらに、その境界に潜む“隠れ固定費”に目を向けることで、大きなコスト削減のチャンスを得られます。
加えて、月次損益計算書の横比較、比率分析、部門別の経費紐づけといったチェックポイントを活用すれば、数字に基づいた判断が可能になります。そして、一時的な削減ではなく、レビュー会議やKPI化、外部パートナーの活用を通じて「仕組み」として定着させることが、継続的な成果につながります。
経営者にとって最も重要なのは、「数字を味方につける」姿勢です。感覚や慣習に頼らず、固定費・変動費を冷静に見直し、仕組み化して管理することで、会社はより強靭で利益を生みやすい体質へと変わります。まずは、自社の数字を丁寧に見直すところから、取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。









