試算表の見方がわからない社長へ!経営に役立つ3つのチェックポイント
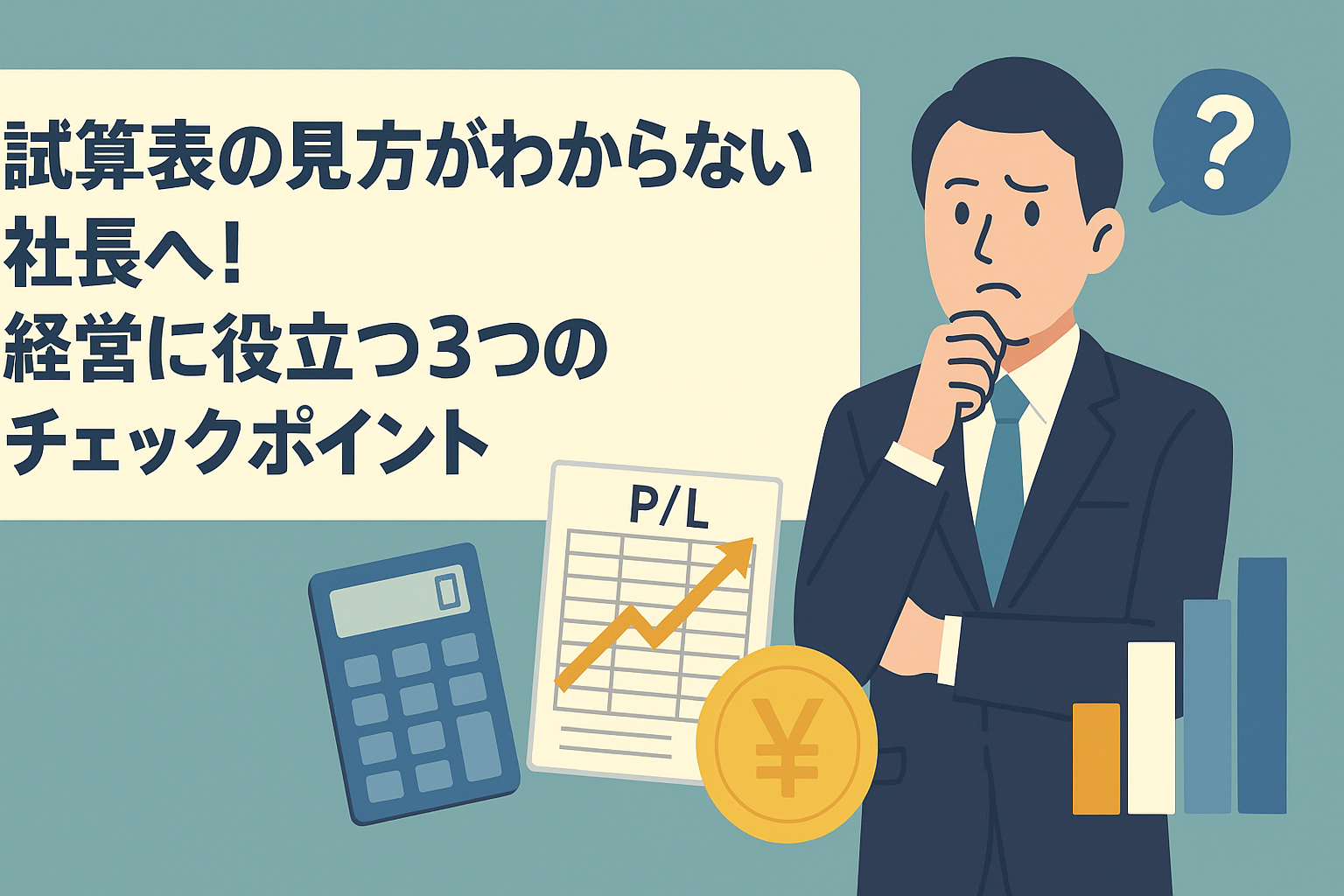
「試算表って、税理士から毎月送られてくるけど、正直どこを見ればいいのかわからない」
そう感じている起業間もない社長は、とても多いものです。
特に創業5年未満の企業では、営業活動や資金調達、採用など日々の業務が最優先になり、経理や会計は後回しになりがちです。試算表が届いても、「数字がずらっと並んでいるだけの資料」としか見えず、そのまま机の引き出しやファイルにしまい込んでいる方も少なくありません。
しかし、試算表を理解せずに経営を続けることは、地図を持たずに航海するようなものです。どれだけ優れた直感を持っていても、数字を把握しなければ「今の会社の位置」と「行き先」を見誤ってしまいます。その結果、資金繰りの悪化に気づけず、倒産や経営危機に陥るリスクすらあります。
この記事では、会計に苦手意識を持つ社長に向けて、試算表の基本的な位置づけと、経営に役立つ3つのチェックポイントをわかりやすく解説します。難しい会計用語を覚える必要はありません。数字が読めるようになれば、経営の意思決定が格段にしやすくなり、未来の不安を減らすことができます。
試算表とは?経営に欠かせない「会社の健康診断書」
まずは、試算表とは何かを正しく理解することが重要です。試算表は、経営者にとって毎月手にできる「会社の健康診断書」と言えます。
試算表とは何か?:会社の財務状況を定期的にチェックするツール
試算表とは「会社の経営成績と財務状態を、月ごとに確認できる数値資料」です。
主に次のような内容で構成されています。
- 損益計算書(P/L):売上から経費を差し引き、最終的に利益がいくら残ったか、又は、いくら赤字になったかを示す
- 貸借対照表(B/S):会社の資産・負債・自己資本を示す
- キャッシュフロー計算書:利益や損失ではなく、お金の流れを把握できる資料
たとえば、営業活動を続けて「売上は順調だ」と思っていても、試算表の損益計算書を見れば、人件費や外注費がかさみ、経常利益が赤字になっていることに気づくケースもあります。
また、貸借対照表やキャッシュフロー計算書を確認すれば、手元資金が少なく、支払いに追われて資金ショート寸前だった、という現実に気づくこともあります。
つまり、試算表は会社の現状を「見える化」し、経営のリスクや課題を浮き彫りにする鏡なのです。
決算書との違い:試算表は「今」を知るための資料
試算表とよく比較されるのが「決算書」です。両者は似ているようで、その役割は大きく異なります。
- 決算書
年に1回決算期に作成し、株主や金融機関、税務署など社外向けに提出する正式な財務報告書。 - 試算表
毎月作成し、経営者が会社の現状を把握するために使う内部資料。スピーディーに現状を知り、経営判断に活かすためのもの。
例えるなら、決算書は「学期末の通知表」であり、試算表は「毎日の体温計や血圧測定」のような存在です。通知表を見て反省しても、その時点ではすでに1年が終わっています。一方で、体温や血圧は日々測定してこそ、体調を崩す前に手を打てます。
社長が試算表を読むべき理由:感覚経営からの脱却
経営者にとって、「勘」や「現場感覚」は大きな武器です。顧客の反応や市場の動向を肌で感じ、素早く意思決定できる力は、まさに起業家の強みです。
しかし、事業が拡大するにつれ、感覚だけに頼った経営には限界が訪れます。
従業員が増え、仕入や外注費も膨らみ、金融機関からの借入も発生する中で、数字を見ずに経営していると、次のような問題が起きやすくなります。
- 「売上は伸びているのに、利益が出ていない」
- 「黒字のはずなのに、現金が足りず支払いに追われる」
- 「借入金の返済が重く、投資に資金を回せない」
これらはすべて、試算表を読み解くことで早期に気づける問題です。
たとえば、ある製造業の社長は「受注が増えているから大丈夫」と考えていました。しかし、試算表を確認すると、外注費の増加で経常利益が赤字に転落していたのです。すぐに外注契約の見直しと生産効率化に取り組んだ結果、翌月には黒字を回復できました。
このように、試算表は経営の「警報装置」であり「羅針盤」です。
数字を把握していなければ、会社の未来を守ることはできません。
早い段階で試算表を読む習慣を身につけることが、会社の成長スピードを加速させます。次の章では、会計初心者の社長でもすぐに実践できる「3つのチェックポイント」を具体的に紹介していきます。
社長が見るべき試算表の3つのチェックポイント
試算表は、数字に慣れていない経営者にとっては「複雑でわかりにくい資料」と感じられることが少なくありません。しかし、すべての数字を理解する必要はありません。経営に直結する「要点」を押さえるだけで十分です。
特に創業5年未満の企業においては、売上の拡大に比べて資金繰りや利益管理が不安定になりやすい時期です。そのため、経営者が最低限注目すべきポイントは、①経常利益、②資金繰り、③比較値(前年対比・予算比・競合他社比)の3つです。
これらを毎月確認するだけでも、試算表は単なる会計書類から「経営の羅針盤」へと変わります。
①利益:売上よりも「経常利益」に注目しよう
試算表を見るとき、多くの社長が真っ先に目を向けるのは「売上」です。もちろん売上は会社の成長を示す重要な指標ですが、売上だけを見て経営の健全性を判断するのは極めて危険です。
なぜなら、売上が増えていても、経常利益が赤字であれば会社の財務体質は悪化していくからです。
経常利益とは何か
経常利益とは、売上から仕入原価や人件費、販売管理費などの経費を差し引き、さらに営業外収益・費用(利息や雑収入、支払利息など)まで反映した後の利益のことです。つまり、会社がどれだけの利益を継続的に生み出せているかを示す指標です。
この経常利益は、企業の稼ぐ力を総合的に表す数値であり、金融機関や投資家が会社を評価する際にも必ず注目する項目です。
経常利益に注目すべき理由
- 本業の収益力が見える
営業活動やサービス提供を通じて、会社が安定して利益を上げられているかを確認できる。 - 将来の成長可能性を判断できる
経常利益が安定的に積み上がっていれば、内部留保の増加や投資余力が生まれる。 - 金融機関からの信頼に直結する
銀行は経常利益の赤字が続く会社には追加融資を行いにくくなる。
確認のポイント
- 単月の経常利益だけでなく、累計や前年同月比をあわせて見る
- 利益率(売上に対する経常利益の割合)を把握する
- 赤字が続いていないか、黒字の安定性があるかを確認する
売上ではなく経常利益こそが経営の実力を表す数値であり、最優先で確認すべき項目です。
②資金繰り:現預金残高と売掛金・買掛金のバランスを確認
経常利益が黒字でも、会社が倒産することがあります。その最大の原因は、現預金が不足することです。これを「黒字倒産」と呼びます。
資金繰りを見るべき理由
- 現金が会社の生命線である
利益があっても現金がなければ、仕入や人件費の支払いができず、取引が止まってしまう。 - 売掛金と買掛金のタイミングがズレやすい
売上計上と現金回収、仕入計上と現金支払のタイミングに差があると、資金繰りが悪化する。 - 突発的な支払いに備える必要がある
税金、賞与支給、大口の仕入れなどは、まとまった資金を必要とする。
確認のポイント
- 現預金残高
月末時点での手元資金を確認し、翌月以降の支払いに耐えられるかを判断する。 - 売掛金と買掛金のバランス
売掛金(未回収の売上)が増えすぎていないか、買掛金(未払いの仕入)が膨らみすぎていないかを確認する。 - 短期借入金の返済状況
毎月の返済負担が資金繰りに与える影響を把握する。
資金繰りを軽視すると、どれだけ利益を上げても会社が持続できなくなります。利益と同じくらい、現金の動きを管理する意識を持つことが必須です。
③比較:前年対比・予算比・競合他社比で相対評価する
最後のチェックポイントは、比較です。試算表の数字は単独で眺めるだけでは十分な意味を持ちません。大切なのは、基準を設けて比較することです。
前年対比
前年同月や前年累計と比較することで、会社の成長スピードや変化の傾向が明確になります。たとえば、売上や経常利益が前年を下回っていれば、その要因を突き止め、改善策を検討する必要があります。
予算比
経営計画で設定した予算と比較することで、計画通りに進んでいるかを把握できます。計画との差異を見つけることは、次のアクションを決めるうえで重要です。差異がプラスであれば成長余力の確認、マイナスであれば早期の軌道修正が必要となります。
競合他社比
同業他社と比較することで、自社の強みや弱みを客観的に把握できます。公開情報や業界平均を参考にし、自社の利益率や成長率が業界水準と比べてどうなのかを確認することが効果的です。
比較が重要な理由
- 変化に気づく
単月の数字だけでは見えない成長や悪化のトレンドを早期に把握できる。 - 計画の精度を高める
予算との差異を分析することで、次年度の計画がより現実的なものになる。 - 競争力を強化できる
業界平均と比較することで、自社が改善すべき領域が明確になる。
比較を取り入れることで数字は「単なる記録」から「行動の指針」へと変わるのです。
試算表を活かすために社長が取るべきアクションとは?
試算表を読む目的は「数字を理解すること」ではなく、理解した数字を経営に活かすことです。
どれだけ試算表を眺めても、それを実際の意思決定に結びつけなければ経営改善にはつながりません。
ここでは、社長が試算表を最大限に活用するために取るべきアクションを3つに整理して解説します。
① 会計事務所や経理外注会社との連携を深め、定期的に数字を見直す
試算表は、多くの場合、税理士や会計事務所・経理代行会社が作成して毎月社長に届けられます。
しかし、資料を受け取るだけで終わらせてしまうと、その価値の大半を失うことになります。
会計事務所等との連携を強める意味
- 数字の背景を説明してもらうことで、理解が格段に深まる
- 異常値やリスクを専門家の視点から指摘してもらえる
- 将来の資金繰りや利益計画についてアドバイスを受けられる
数字を読むことに慣れていない社長にとって、会計事務所等は「経営の伴走者」とも言える存在です。数字を一緒に見ながら現状を振り返る習慣を作るだけで、経営判断のスピードと精度が高まります。
実践のポイント
- 毎月、試算表が届いたら必ず30分〜1時間の打ち合わせを設ける
- 分かっていないと思われることを恐れず、「なぜこの数字になったのか」を必ず確認する
- 自社の経営課題に直結する数字を一緒に見つけてもらう
試算表は数字の専門家と共に読み解いてこそ最大限の効果を発揮するのです。
② 社内の経理体制を整えるか、外部の力を借りる
試算表を活用するうえで、次に重要なのは「誰が数字を管理するのか」です。
社長自身が数字をチェックするのは当然ですが、作成や管理を社内で適切に担う体制がなければ、正確でタイムリーな試算表は得られません。
社内経理体制の課題
- 経理担当者がいない、あるいは兼務で手が回らない
- 担当者が退職するとノウハウが失われる
- 入力や集計の遅れで、試算表が数か月後にしか出てこない
このような状況では、せっかくの試算表が経営判断に役立ちません。
解決策としての外部活用
- バックオフィス代行サービスを利用し、経理業務を外注化する
- 専門家に任せることで、正確でスピーディーな試算表が得られる
- 社長や社内人材は経理業務から解放され、数字の確認と意思決定に専念できる
特に創業間もない会社では、経理担当者を雇用するよりも外部に依頼する方がコスト効率も高く、安定的な運用が可能です。
試算表を「活きた経営資料」として活用するには、社内外を問わず適切な経理体制を整備することが不可欠です。
③ 経営の「見える化」で、会社の未来が描きやすくなる
試算表の数字を社長だけが理解していても、会社全体の成長にはつながりにくい場合があります。
重要なのは、数字をもとに経営を「見える化」し、社員や関係者と共有することです。
見える化がもたらす効果
- 社員の納得感が高まる
経営状況が数字で示されると、方針や施策の理由が理解しやすくなる。 - 行動が数字に結びつく
営業や現場が「自分たちの努力が利益や賞与にどう影響するか」を理解できる。 - 将来の計画が立てやすくなる
過去と現在の数字をもとに、現実的な目標や投資判断が可能になる。
実践のポイント
- 毎月の試算表から要点を抜き出し、社内で共有する
- 重要な指標(利益、資金繰り、比較結果)をグラフ化し、視覚的に理解できるようにする
- 数字を根拠にした経営計画を策定し、社員と方向性を共有する
試算表を「社長だけのもの」から「組織全体の経営ツール」へ変えることで、会社の未来はより明確に描けるようになります。
「試算表が読めない社長」から卒業しよう
試算表は単なる会計資料ではありません。
試算表は、会社の健康状態を把握し、未来をつくるための経営ツールです。
会計が苦手な社長は、まず試算表で確認すべきは、
- 経常利益(儲けの実力)
- 資金繰り(現金の流れ)
- 比較(前年対比・予算比・競合他社比)
の3つに絞られます。
そして、それを経営に活かすためには、
- 会計事務所と連携して数字を読み解く
- 社内経理体制を整備するか外部サービスを活用する
- 数字を見える化して社員と共有する
という3つのアクションが不可欠です。
「試算表の見方がわからない」という状態を乗り越えれば、数字は経営者にとって最も頼もしい味方になります。
数字を根拠にした意思決定ができるようになれば、会社の将来像はより鮮明になり、安心して次の一歩を踏み出すことができるでしょう。









