銀行に信頼される会社になる!融資に強い経理体制の作り方
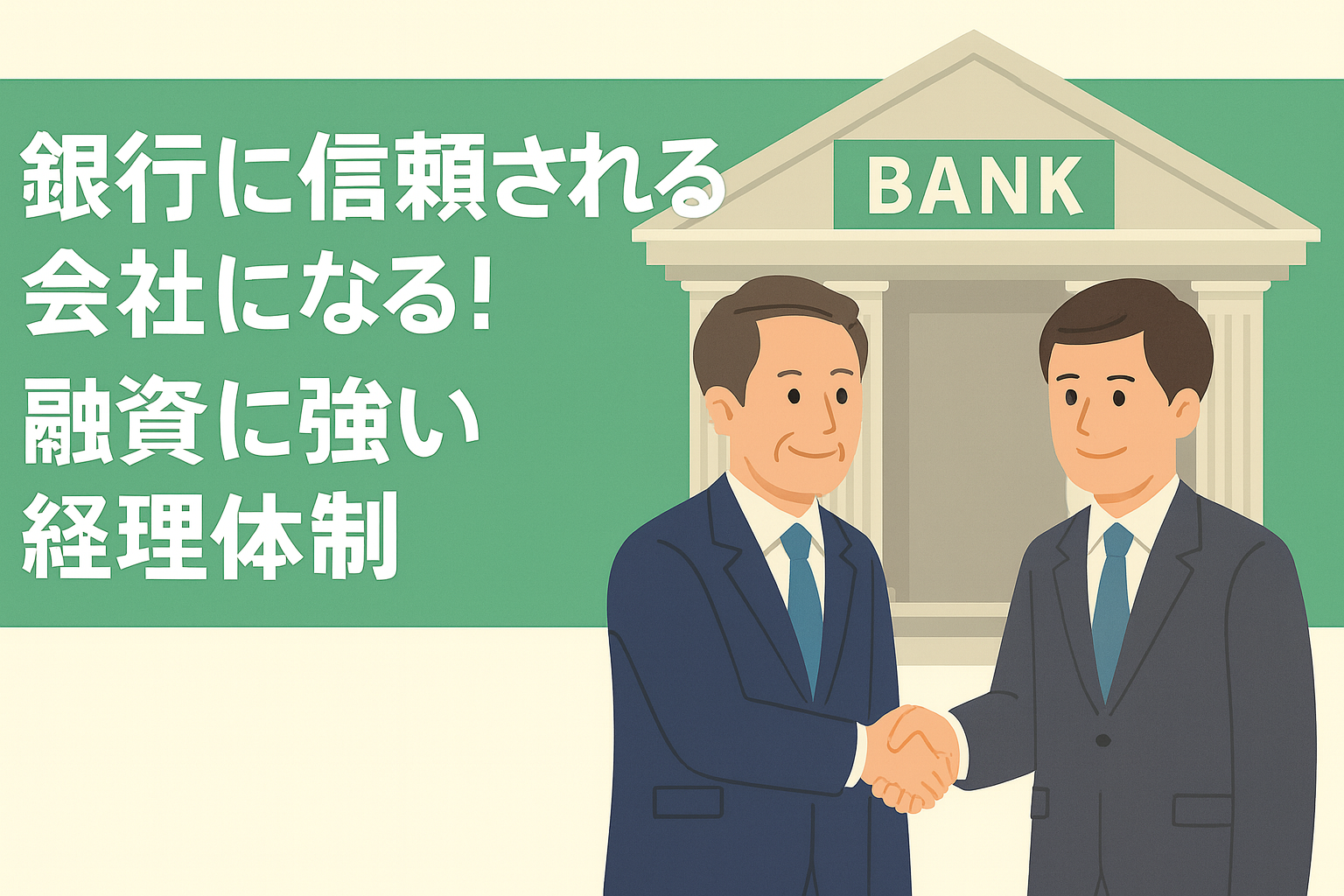
銀行からの融資をスムーズに受けるためには、事業の将来性だけでなく、経理体制の信頼性が大きな判断基準となります。多くの中小企業では「決算書を作って提出する」ことが目的化しており、銀行が本当に見ているポイントを理解できていないケースが少なくありません。
「うちは黒字だから問題ないはず」と考える経営者の方も多いのですが、実際には黒字でも融資がスムーズに進まないことがあります。その理由の多くは「経理体制」そのものにあります。数字が正しく、タイムリーに整理されているかどうか、経営者自身が数字を理解しているかどうか。これらは銀行が企業の信頼度を測るうえで欠かせない要素です。
銀行に信頼されるかどうかは、決算書や試算表の内容だけでなく、それを生み出す「仕組み」によって大きく左右されます。裏を返せば、正しい経理体制を整えれば、銀行は必ず会社を高く評価してくれるということです。
本記事では、銀行が経理体制をどのように評価しているのかを明らかにし、さらに信頼される経理体制をつくる具体的なステップを紹介していきます。単なる知識の解説ではなく、実際の融資の現場で役立つ考え方や実践的なノウハウを交えながら解説しますので、自社の経理を振り返りながら読み進めていただければと思います。
なぜ銀行は経理体制を見ているのか?信頼の基準を知る
銀行が融資の可否を判断するとき、最も重視するのは「返済能力」です。しかし、その返済能力を判断する材料となるのが、会社の財務情報です。つまり、経理体制の整備度合いが、そのまま銀行の信頼に直結します。
経営者の中には「事業が順調なら銀行はお金を貸してくれるだろう」と考える方もいますが、銀行は感覚や雰囲気では判断しません。必ず、客観的なデータを基に融資を検討します。そして、そのデータの信頼性を支えるのが経理体制なのです。
以下では、銀行が経理体制を見るときに特に注目している3つの基準を取り上げます。
銀行が最も重視するのは「財務の透明性」
銀行が第一に見るのは「数字が透明で、隠し事のない状態」になっているかどうかです。
銀行は貸したお金が返ってくるかどうかを判断するために、財務諸表を確認します。しかし、その数字がどのように作られたのかが不透明であれば、いくら利益が出ていても安心して融資をすることはできません。
例えば、売掛金や買掛金の処理が遅れている会社では、帳簿上の利益と実際の資金繰りが乖離してしまいます。そうすると、銀行は「本当に返済できるのだろうか」と不安を抱きます。一方で、日々の取引が正確に記帳され、毎月の試算表がスピーディーに作成されている会社は「財務の透明性が高い」と評価されやすくなります。
実際、ある製造業の経営者が、外部の経理代行を利用して月次決算を導入したところ、それまでよりも融資の審査がスムーズに通るようになった事例があります。銀行担当者からも「数字が早く出るようになったので判断しやすい」と評価を受けたのです。
このように、財務の透明性は融資の可否を大きく左右する要因です。そして、その透明性を支えるのが、正しい経理体制の運用なのです。
決算書・試算表の信頼性が審査を左右する理由
次に銀行が注目するのは、決算書や試算表そのものの「信頼性」です。
単に数字が並んでいるだけでは不十分で、その数字が事実を正確に表しているかどうかが問題となります。銀行は、粉飾や誤りがないか、また会計基準に沿って作成されているかを見極めます。
例えば、売上の計上時期を意図的にずらして一時的に利益を大きく見せるような処理をしてしまうと、銀行はすぐに違和感を覚えます。過去数期分の決算書を比較し、増減の理由を尋ねるからです。そのときに経理や経営者が明確に答えられなければ、「この会社は数字を正しく把握していない」と判断されます。
逆に、毎月の試算表が嘘偽りなく正しく作成され、決算時に大きな修正が入らない会社は「管理がしっかりしている」と見なされます。こうした会社は、財務状況に対する説明責任を果たせるため、銀行からの信用も厚くなるのです。
実際に、ある建設業の企業では、以前は決算書が会計事務所任せで内容を把握していませんでした。しかし、自社で月次の試算表を作成できるよう整備し始めたことで、銀行との面談で数字の根拠を自信を持って説明できるようになり、融資枠が拡大したというケースがあります。
このように、決算書や試算表の信頼性は、単なる数字の羅列ではなく「会社がどれだけ自社を理解しているか」を示すものだといえるのです。
経理体制が信用格付けに与える影響とは
最後に見ておきたいのが、銀行の「信用格付け」における経理体制の影響です。
銀行は融資先をランク付けし、それに応じて融資条件(金利や融資額)を決めています。この格付けは、財務内容だけでなく、定性的な要素も加味されます。その中で「経理体制の整備度合い」は非常に重要なポイントとされています。
例えば、帳簿が遅れていたり、経営者が数字を把握していない企業は「内部管理が弱い」と見なされ、格付けが下がる可能性があります。すると、融資が通りにくくなるだけでなく、借りられたとしても金利が高くなったり、条件が厳しくなったりします。
逆に、経理体制が整っており、月次で数字を把握している企業は「経営管理能力が高い」と評価されます。このような会社は格付けが上がり、同じ業績であっても融資条件が有利になります。
あるサービス業の経営者は、内部統制を強化し、経理業務を複数人でチェックできる体制を整えたところ、銀行からの格付けが改善されました。その結果、これまでよりも低い金利で融資を受けられるようになりました。
つまり、経理体制の構築は単なる事務作業の効率化にとどまらず、融資条件そのものを左右する「経営戦略上の武器」となるのです。
ここまで見てきたように、銀行が経理体制を重視する理由は明確です。それは「返済能力を判断するための数字の信頼性を確保する」ことにあります。そして、その信頼性は、財務の透明性、決算書・試算表の正確性、さらには経理体制そのものによって担保されます。
では、具体的にどのように経理体制を整えていけば銀行に信頼される会社になれるのでしょうか。次の章では、その実践的なステップを解説していきます。
銀行に信頼される経理体制を作るための3つのステップ
銀行に信頼される経理体制を作るためには、単に会計ソフトに数字を入力するだけでは不十分です。重要なのは、経理を「未来の経営判断や融資につながる情報基盤」として活用できる状態にすることです。ここでは、銀行からの評価を高めるために必要な3つのステップを整理します。
ステップ① 正確かつリアルタイムな会計処理を整える
まず第一に必要なのは「会計処理の正確さ」と「スピード」です。銀行は、過去の決算書だけでなく直近の試算表や資金繰りの状況を確認します。そのため、会計処理が遅れている会社は「経営の現状を正しく把握していない」と見なされ、信頼を失う可能性があります。
例えば、請求書や領収書の入力が翌月末にまとめて行われているようなケースでは、集計の遅れが発生します。その結果、収支や資金繰りの見通しが立たず、銀行への説明もあいまいになりがちです。
これに対して、日々の会計処理をリアルタイムで進めていれば、銀行から「この会社は常に正確な数字を把握している」と評価されます。加えて、早期に異常を発見できるため、不良債権の回収や過剰な支出への対応も迅速になります。
実際、ある小売業の経営者は、クラウド会計ソフトを導入してリアルタイムで売上と支出を把握できるようにした結果、銀行との面談で即座に数字を提示できるようになりました。そのことで担当者から「管理がしっかりしている」と高く評価され、融資枠の拡大につながったのです。
したがって、最初のステップは「正確でタイムリーな会計処理」を徹底することです。これが銀行との信頼関係を築く土台となります。
ステップ② 内部統制と業務フローの整備が信頼性を高める
次に必要なのは「内部統制」と「業務フローの整備」です。どれだけ数字が早く出ても、その信頼性が担保されていなければ意味がありません。銀行は「その数字が誤りや不正なく作成されているか」に注目します。
経理業務が一人の担当者に依存している場合、入力ミスや意図的な改ざんが発生しても気づきにくいものです。また、経理担当者が突然退職したときに業務がストップしてしまうリスクもあります。これらは銀行にとって「内部管理が脆弱な会社」と見なされる要因になります。
そこで重要になるのが、複数人によるチェック体制や明確な業務フローです。たとえば、請求書の発行は営業部が行い、入金確認は経理が担当し、月次の締めは上長が承認するといったように、業務を分担し相互にチェックできる仕組みを整えることが求められます。
あるIT企業では、以前は経理担当者ひとりがすべての処理を行っていましたが、内部監査の観点から承認フローを導入しました。その結果、数字の正確性が向上し、銀行からも「体制が強化された」との評価を受けました。
ステップ③ 経営者自身が数字を理解することが不可欠
最後のステップは「経営者自身が数字を理解していること」です。これは銀行との関係において最も重要なポイントです。
銀行との面談の場で、経営者が決算書や試算表の内容について具体的に説明できるかどうかは、融資担当者が強く注目する点です。経営者が「その部分は経理担当に聞いてください」と答えてしまうと、「この会社のトップは自社の財務に責任を持っていない」と見なされ、評価が下がる可能性があります。
逆に、経営者自身が数字を深く理解していれば、銀行は「この経営者なら資金を正しく運用できる」と安心します。数字を根拠に今後の投資計画や返済計画を語れる経営者は、信頼性が非常に高いと判断されるのです。
たとえば、ある建設業の社長は、自ら資金繰り表を作成して銀行面談に臨むようになりました。それまでは経理担当に任せきりでしたが、自ら数字を把握することで「今後3か月の資金余力」「未成工事に対する外注業者への先払いが必要な資金の額」などを明確に説明できるようになりました。その結果、銀行担当者から「経営者として安心できる」と評価され、追加融資の承認が下りやすくなったのです。
結論として、経理体制の整備を進めるうえで最終的に必要なのは「経営者の数字に対する責任感と理解力」です。どれだけ優秀な経理スタッフや外部専門家を活用しても、経営者が数字に無関心であれば銀行は信頼を寄せません。
以上の3つのステップ、すなわち
- 正確かつリアルタイムな会計処理
- 内部統制と業務フローの整備
- 経営者自身の数字理解
これらを実行することで、銀行に「信頼される経理体制」の構築を実現することができます。
では、こうした体制を整えるにあたり、自社のリソースだけで実現できるでしょうか。実際には、中小企業では人的リソースやノウハウの不足から難しいと感じる企業が少なくありません。次章では、その課題を解決するための「外部リソース活用術」について解説します。
信頼される会社に変わるための外部リソース活用術
銀行に信頼される経理体制を作るためのステップは理解できても、実際に自社だけで完結するのは難しいと感じる経営者は少なくありません。経理担当者の採用・育成には時間もコストもかかり、属人化のリスクも大きいのが現実です。そんなときに有効なのが、外部リソースの活用です。ここでは、経理体制を強化するために活用できる具体的な手段を紹介します。
経理業務の属人化がもたらすリスクとその回避法
経理業務を一人の担当者に依存することは、銀行からの信頼を損ねる最大の要因のひとつです。
経理担当者が突然退職した場合、数字の引き継ぎができずに決算が遅れることがあります。銀行に提出する書類が遅れれば、「この会社は内部管理が脆弱だ」と判断され、融資が難しくなることも珍しくありません。また、特定の担当者に情報が集中していると、不正や誤りを発見できないリスクも高まります。
こうした属人化のリスクを避けるためには、複数人によるチェック体制を整えることが理想ですが、中小企業では人員の制約から難しいケースが多いでしょう。そこで有効なのが「外部の専門家やサービスを併用する」方法です。
例えば、会計事務所や経理代行サービスを活用することで、担当者がいなくても数字を正しく処理できる環境を維持できます。また、専門家によるダブルチェックが入ることで、経理データの信頼性も一段と高まります。
実際、ある製造業の会社では、長年一人の経理担当者に任せきりにしていた結果、退職時に大きな引き継ぎトラブルが発生しました。その後、経理代行サービスを導入したことで、数字の透明性が確保され、銀行からも「以前よりも体制が安定した」と評価されるようになりました。
つまり、属人化のリスクを回避すること自体が、銀行からの信頼を得るための大きな一歩となります。
バックオフィス代行の活用が経理の信頼性を高める
次に弊社が提供している「バックオフィス代行サービス」を詳しく説明させていただきます。
バックオフィス代行とは、会計記帳、給与計算、請求・支払い管理といった経理業務を外部に委託し、正確かつ効率的に処理してもらうサービスです。この仕組みを利用することで、経理の正確性とスピードを両立でき、銀行に対して「数字を常に正しく把握している会社」としてアピールできます。
特に中小企業にとっては、社内に専門知識を持つ人材を複数人確保するのが難しいため、専門的なノウハウを持つ外部に任せることは合理的です。バックオフィス代行を導入すれば、月次決算で作成する試算表の提出スピードが格段に向上し、銀行面談でもリアルタイムのデータを提示できるようになります。
例えば、あるIT系スタートアップでは、経営者が営業や開発に専念するあまり、経理が後回しになり、決算処理が大幅に遅れることがありました。しかし、バックオフィス代行を利用することで、毎月の試算表が自動的に整備されるようになり、銀行から「経理管理が改善された」との評価を受けました。その結果、融資審査のスピードも早まり、資金調達のタイミングを逃さずに済んだのです。
さらに、バックオフィス代行は単なるアウトソーシングにとどまらず、業務フローの見直しや効率化にも寄与します。これにより、経理体制全体の信頼性が底上げされ、銀行からの長期的な評価も向上していきます。
CFO・COO代行の活用でさらに高まる金融機関からの信頼
経理業務のアウトソーシングに加えて、より戦略的に活用できるのが「CFO・COO代行」です。
CFO代行は、財務責任者の役割を外部の専門家に担ってもらうサービスで、資金調達戦略や財務分析、銀行対応などをプロの視点でサポートしてくれます。銀行との面談にも同席し、金融機関が納得する説明をしてくれるため、融資交渉が格段に有利になります。
また、COO代行は業務全体の効率化や組織体制の強化を支援してくれるため、経理だけでなくバックオフィス全体の信頼性を底上げする効果があります。銀行は「この会社は経営体制がしっかりしている」と評価しやすくなり、結果として信用格付けの向上にもつながります。
あるサービス業の中小企業では、CFO代行を導入したことで資金繰り表の作成が習慣化し、銀行面談で将来の資金需要を具体的に説明できるようになりました。その結果、これまで以上にスムーズに追加融資を受けられるようになったのです。
融資に強い会社になるために
経理体制の整備は、単なるバックオフィス業務の効率化だけではありません。それは「銀行に信頼され、必要なときに必要な資金を迅速に調達できる会社」になるための経営戦略そのものです。
ここまで見てきたように、銀行に信頼される経理体制を築くためには、
- 財務の透明性を確保する
- 決算書・試算表の信頼性を高める
- 内部統制や業務フローを整備する
- 経営者自身が数字を理解する
といったステップが欠かせません。
しかし、これらをすべて自社で実行するのは容易ではありません。だからこそ、バックオフィス代行やCFO・COO代行といった外部リソースを活用することが、銀行からの信頼を短期間で獲得する現実的な方法となります。
経理体制を整備することは「コスト」ではなく「投資」です。銀行からの融資条件が改善され、資金繰りが安定すれば、事業拡大のチャンスを逃さずに済みます。そして何より、金融機関から信頼される会社は、取引先や社員からも「安心できる会社」と評価されるのです。
今こそ、自社の経理体制を振り返り、「銀行に信頼される会社」へと変わる第一歩を踏み出すときです。未来の成長資金を確実に手にするために、今日からできる改善に着手してみてください。









